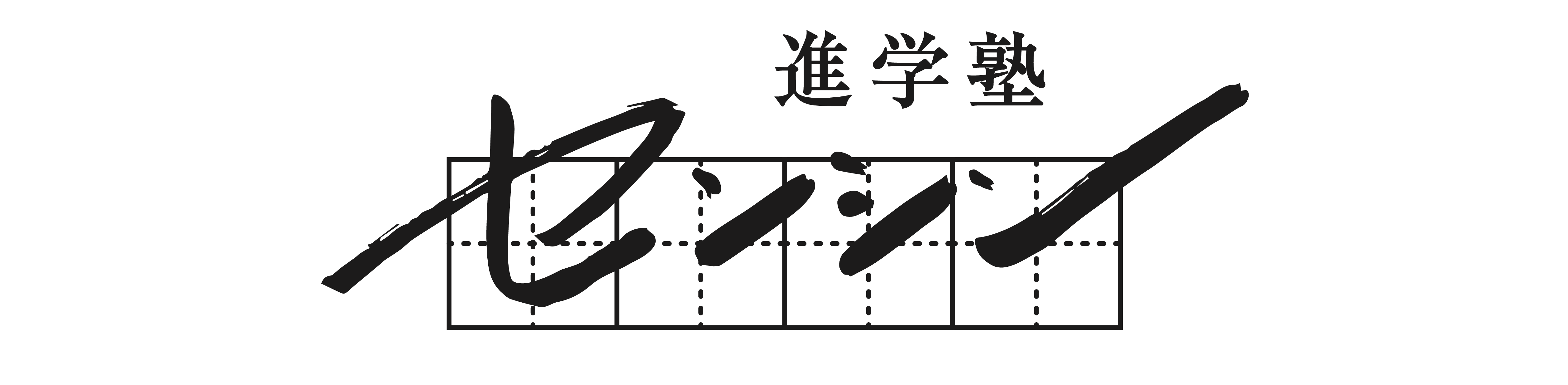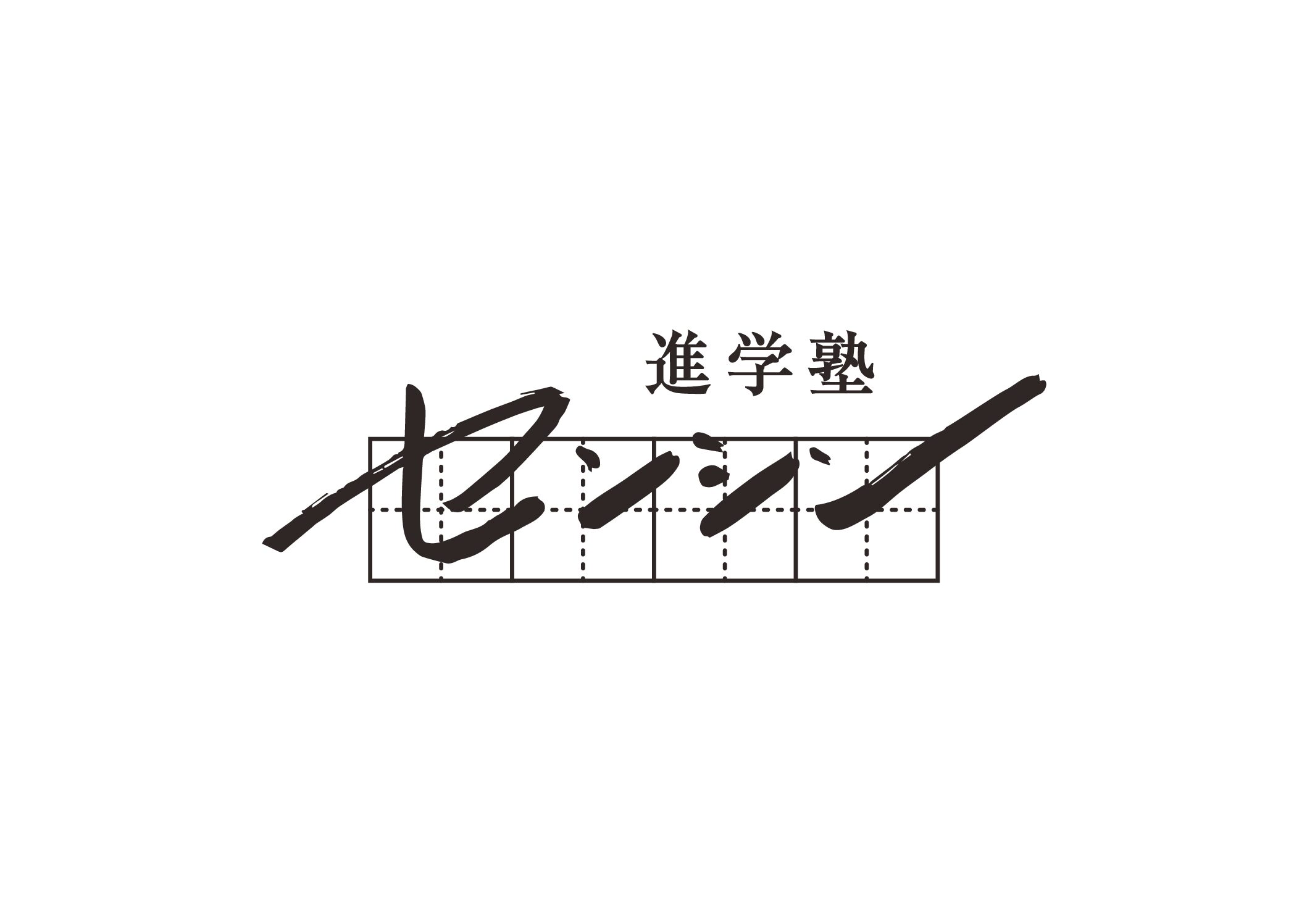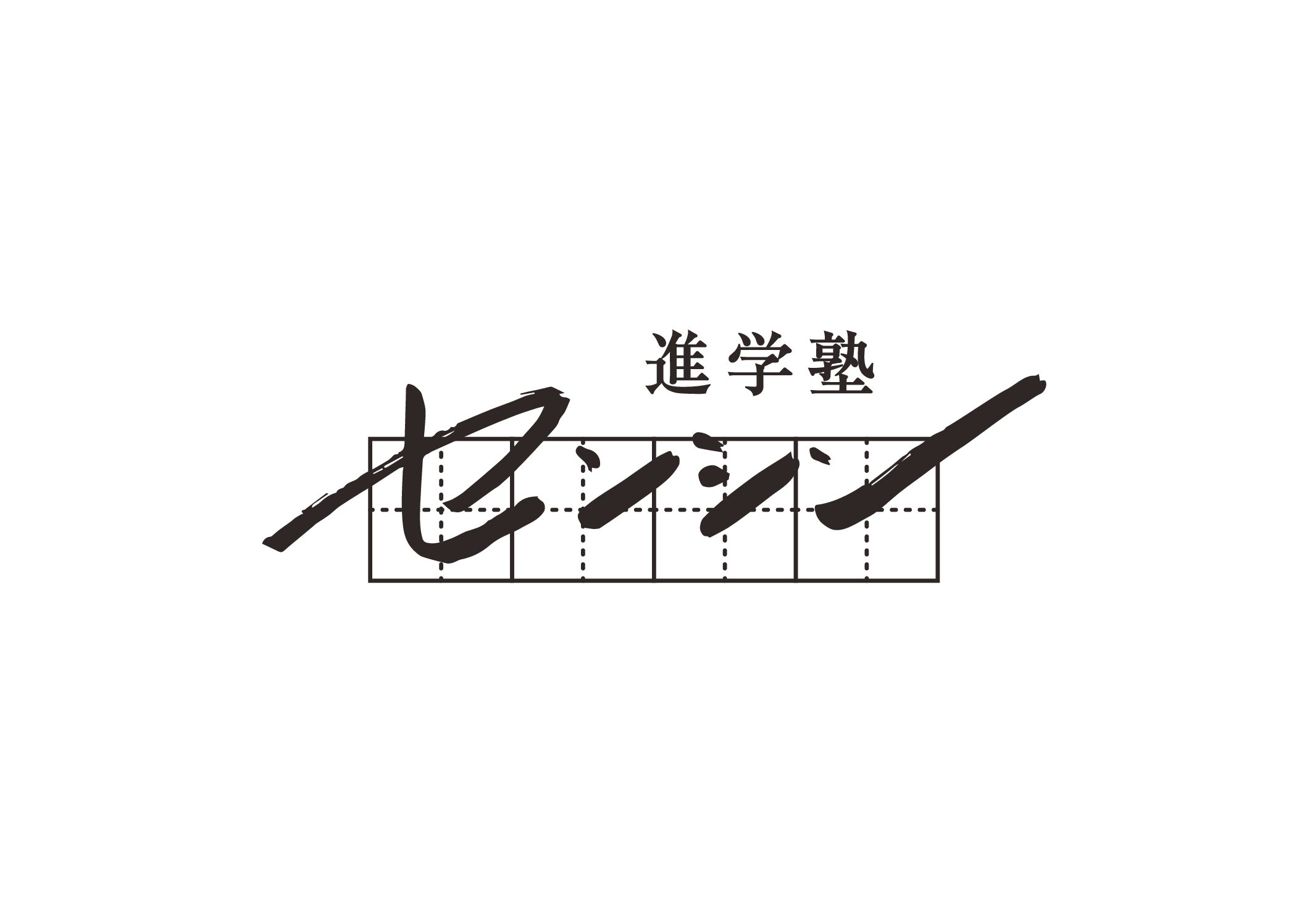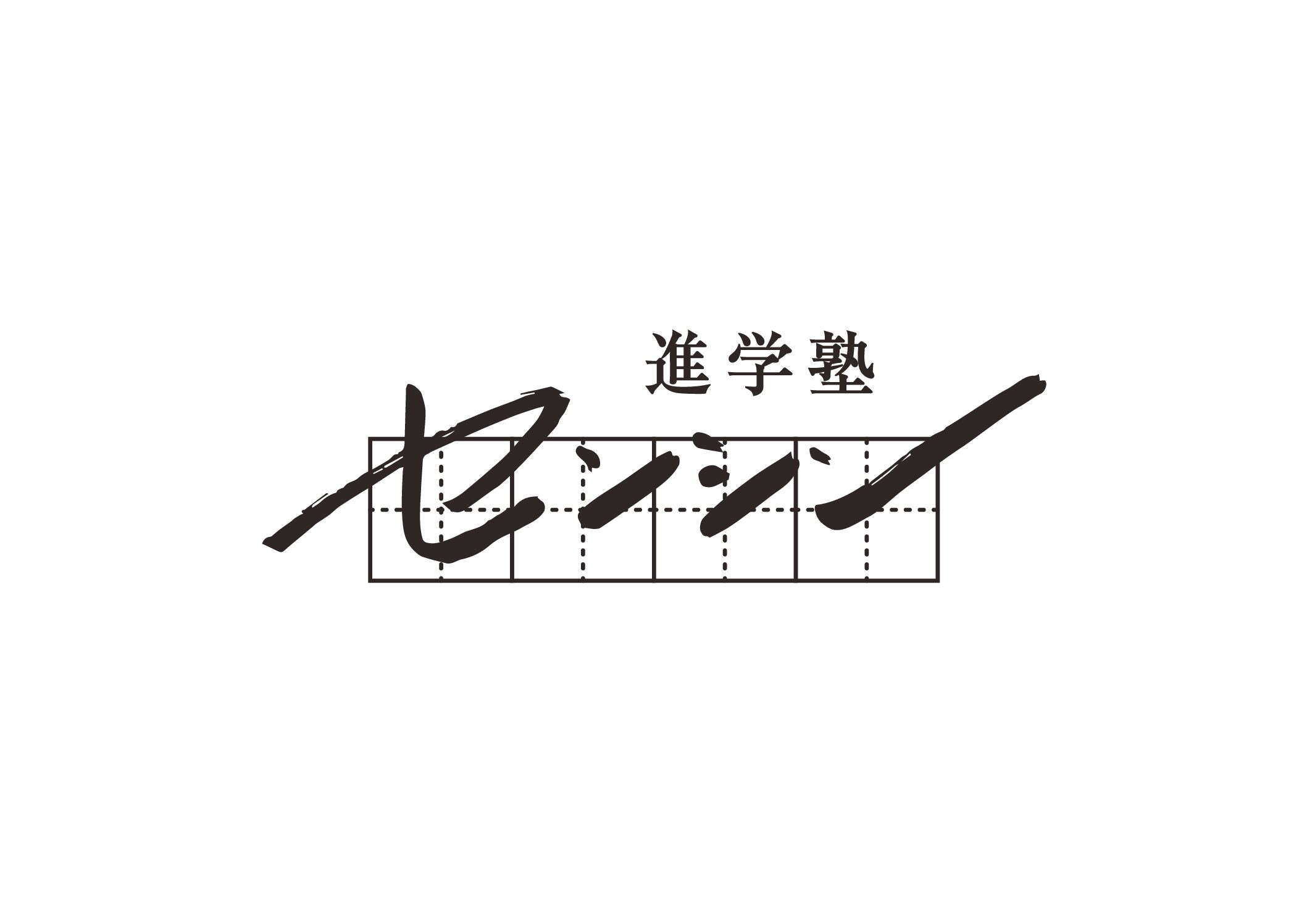「物体は力が働かないかぎり、静止し続ける」。
これが我々の日常的感覚です。
しかし、17世紀初めにガリレオ=ガリレイが「そうじゃない、等速直線運動をし続けるんだ」と言い出します。つまり床を転がるエンピツは、力が働かないかぎり、宇宙の果てまで転がり続けるというのです。
当時の人々も多くがこの説に反対しました。
が、やがてニュートンがこの説を組み込んで力学をつくり、地上の物体も天体も見事に説明したことで流れは変わります。ガリレオやニュートンの方法は近代科学と呼ばれ、いまでは等速直線運動は中学で習うようになりました。
また、「英単語ひとつひとつには、それに対応した日本語訳がある」とも、我々日本人は考えています。
しかし20世紀初め、ソシュールという言語学者が「ちがう。コトバそのものと、コトバの意味との結びつきは、各言語によってまちまちなんだ。だから『blue』=『青』ではない」と主張します。つまりblueと青では、意味の幅が微妙に異なるのです。
その後、構造主義の考え方が世界中に広まるにつれ、ソシュールの説も受け入れられていきました。いまでは、虹が何色に見えるかは国によって異なることが知られています。
以上2つの例から見たとおり、学問の進展は、それまでの常識を疑うところから始まります。学問だけでなく、この世界のルールや慣習、日々のニュースや生活で常識とされていること。そのなかに「本当にそうだろうか」と疑問に思うことがあったなら、その疑問を大切にしてください。
そして、疑問に思う対象を選ぶ力。これが教養です。やがて「学問」に触れるその日まで、今は「勉強」して教養を増やしましょう。
進学塾センシン
塾だより2021年10月号より
*生徒・保護者向けに月一で発行している「塾だより」から、主要な記事を抜粋して公開しています。
←前の記事「学力の停滞期」
次の記事「情報を遮断し、情報を選ぶこと」→